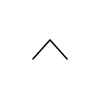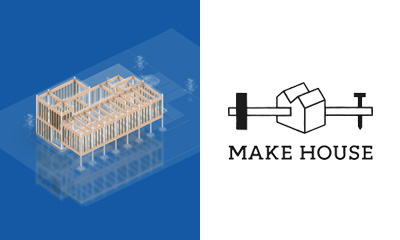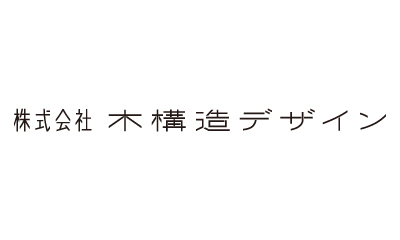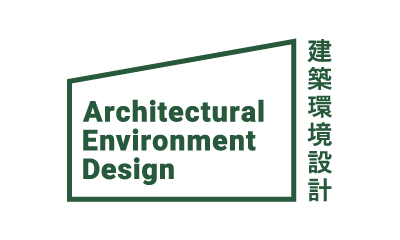【山形県】中大規模木造の実務ポイントとSE構法の技術
山形県では近年、非住宅用途の木造建築に対しても県産木材の活用が積極的に推進されています。
公共施設や商業施設、観光拠点など多様な建築で地元の森林資源を生かす試みが進み、積雪寒冷地に適した構造設計と断熱対策が求められる一方、伝統技術と最新技術の融合によって耐久性と機能性を両立しています。
学校や道の駅、図書館など地域の拠点施設において採用事例が増え、木の温もりと県産材活用の意義を住民や来訪者に広く伝える役割も担っています。
また、脱炭素社会を見据えた環境負荷低減の観点から期待されるだけでなく、林業や関連産業の活性化にもつながる点も大きいです。
さらに、県内の建築事業者や設計事務所は、伝統工法を継承しつつ耐震・省エネ基準を満たす先進的な手法を取り入れ、地域文化の保全と持続可能なまちづくりに貢献しています。
この記事では山形県における中大規模木造の実務ポイントとSE構法の技術についてお伝えします。
<このコラムでわかること>
・中大規模木造の普及が進む山形県の特徴
・やまがたの建築物における木材の利用の促進に関する基本方針
・山形県における公共建築物等の木材利用
・山形県の中大規模木造に最適なSE構法の概要
・SE構法へのお問合せ、ご相談について
・まとめ
中大規模木造の普及が進む山形県の特徴

山形県は本州の東北地方に位置し、四方を山に囲まれているため、冬季には多くの地域で豪雪に見舞われる特徴があります。
この厳しい気候条件が、県内の住宅・建築に大きな影響を及ぼしてきました。
例えば、雪の重みや寒さから建物を守るために、屋根の勾配を急にして雪を落としやすくしたり、断熱性能を高める工夫がなされてきました。
特に、山形県の内陸部では気温の寒暖差が大きく、夏には蒸し暑い日が続くため、通風を考慮した伝統的な意匠や庇の活用など、季節ごとの気候に適応した工夫が多く見られます。
また、森林面積が広い山形県では、豊富な木材資源を生かした木造建築が古くから盛んに行われてきました。
県内各地では、杉や桧など地元産の木材を用いた伝統技術が継承され、地場産業としての木工や家具づくりも発展しています。
さらに、豪雪地帯という特性から基礎の高さを確保し、雪かきや排雪をしやすいよう空間設計を工夫するなど、現代の住宅にも伝統的な知恵が取り入れられています。
一方、日本海側に位置する酒田市や鶴岡市などでは、風雨や湿気への対策も重視されてきました。
港町として発展してきた酒田市の商家や蔵の建築は、外壁を厚い漆喰や板張りで保護するなど、湿気と塩害への対策がほどこされています。
また、山形県各地に点在する温泉街では、旅館建築に木造や和風建築の伝統美を活かしつつ、近年では耐震や省エネルギー性能を高める改修が積極的に行われています。
このように、山形県の住宅・建築は、豊かな自然環境と四季の気候変化、そして歴史的背景に支えられて独自の発展を遂げてきました。
重厚な積雪対策から、地元木材を活用した匠の技、湿気や風への対処まで、多様な環境に適応する工夫が詰まっていることが大きな特徴です。
近年では、伝統を守りつつも新技術を取り入れた省エネ住宅や災害に強い設計が注目されており、山形県ならではの風土に根差した家づくりが受け継がれ、さらに発展を続けています。
やまがたの建築物における木材の利用の促進に関する基本方針

やまがたの建築物における木材の利用の促進に関する基本方針は、当初「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物等における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項などについて定められました。
その後、この法律が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、国が木材利用に関する基本方針を策定したことを受け、山形県の方針について変更が行われました。
やまがたの建築物における木材の利用の促進に関する基本方針の主なポイントは下記です。
山形県が豊富に有する森林資源を最大限に生かすための「県産木材の利活用促進」が大きな柱として挙げられています。
地産地消の観点から、地域で伐採された杉や檜などの良質な木材を積極的に住宅や公共施設に活用することで、林業の振興や地域経済の活性化につなげる狙いがあります。
これに関連して、材料調達から加工、施工までを地元事業者で連携する体制づくりの重要性が強調されており、木材の安定供給や品質確保のための管理システムづくりにも取り組む姿勢が示されています。
特に豪雪地帯が多い山形県では、積雪荷重や気密・断熱性に対応した構造計画が求められます。
高断熱・高気密による暖房負荷の軽減や、パッシブデザインの導入といった省エネルギー技術を木造建築にうまく取り入れることで、県内の気候風土に応じた快適な住環境を実現する方策が示されています。
さらに、歴史的木造建築の保存・活用にも言及され、伝統工法や地域固有の設計手法を後世に伝える重要性が強調されています。
文化財指定建築や町並み保存地区などの修復・再生を通じて、匠の技術や地元の建築文化を守りつつ、観光振興や地域コミュニティの活性化にも貢献するとしています。
こうした取り組みは、木造建築における技術継承と地域ブランド向上にも直結します。
一方、施工者側への支援策としては、地域材活用の補助制度や人材育成施策の充実が示され、木造建築に精通した技術者の確保・育成が課題であるとの認識を示しています。
とくに若手・中堅技術者へのノウハウ共有や、新築・リフォームを含む様々な工程での専門性向上を図るための研修プログラムが推奨されています。
「地元資源の活用」「高い安全性・省エネ性能」「伝統技術の継承」「技術者育成と産業振興」を四つの柱として掲げ、木造建築を通じた持続可能な住環境の実現を目指しています。
建築実務者にとっては、これらの方針を踏まえ、地元木材の強みを活かしたデザインや施工体制の整備、さらには耐震・省エネ・伝統技術の融合を図ることが求められると言えます。
関連記事:やまがたの建築物における木材の利用の促進に関する基本方針
山形県における公共建築物等の木材利用

公共建築物は、広く国民一般の利用に供するものであることから、木材を用いることにより、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供することができます。
このため、建築物木材利用促進基本方針では、公共建築物について、積極的に木造化を促進することとしています。
林野庁の資料「森林・林業白書」によると、山形県では下記のように木造率が推移しています。
・2017年度:
建築物全体(57.4%)、公共建築物(30.0%)、うち低層の公共建築物(42.6%)
・2019年度:
建築物全体(61.0%)、公共建築物(27.5%)、うち低層の公共建築物(34.2%)
・2021年度:
建築物全体(54.1%)、公共建築物(14.3%)、うち低層の公共建築物(28.0%)
2022年度以降に整備に着手する国の公共建築物については、建築物木材利用促進基本方針に基づき、計画時点においてコストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、原則として全て木造化を図ることになっています。
山形県の中大規模木造に最適なSE構法の概要

耐震構法SE構法(以下、SE構法)は、大規模木造建築物の技術を基に開発された技術です。
SE構法は構造計算された耐震性の高い木造建築を実現する、独自の建築システムです。
SE構法は耐震性の高さ、設計の自由度、コストパフォーマンスの良さ、ワンストップサービス等で高い評価を受けており、さまざまな大規模木造の実績が増えています。
SE構法は、単純に「剛性のある木質フレーム」というだけではなく、さまざまな利点を追求し、大規模木造で求められる大空間・大開口を可能にして、意匠設計者の創造性を活かせる設計の自由度を提供しています。
関連記事:耐震構法SE構法は全棟で立体解析による構造計算を実施
SE構法は「木造の構造設計」と「構造躯体材料のプレカット」そして施工というプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。その合理的なシステムが、設計・施工のプロセスにおいて納期や工期の短縮につながります。
関連記事:「ウッドショック等のリスクにSE構法のワンストップサービスが強い理由」
SE構法へのお問合せ、ご相談について

大規模木造をSE構法で実現するための流れは下記となります。
1.構造設計
SE構法を活用した構造提案を行います。企画段階の無料の構造提案・見積りから、実施設計での伏図・計算書作成、確認申請の指摘対応等を行っております。また、BIMにも対応可能です。
2.概算見積り
SE構法は構造設計と同時に積算・見積りが可能です。そのため躯体費用をリアルタイムで確認可能で、大規模木造の設計において気になる躯体予算を押さえつつ設計を進めることが可能です。
3.調達
物件規模、用途、使用材料を適切に判断して、条件に応じた最短納期で現場にお届けします。また、地域産材の手配にも対応しております。
4.加工
構造設計と直結したCAD/CAMシステムにより、高精度なプレカットが可能です。また、多角形状、曲面形状などの複雑な加工形状にも対応可能です。
5.施工
SE構法の登録施工店ネットワークを活用し、計画に最適な施工店を紹介します。(元請け・建方施工等)
6.非住宅版SE構法構造性能保証
業界初の非住宅木造建築に対応した構造性能保証により安心安全を担保し、中大規模木造建築の計画の実現を後押しします。
↓SE構法へのお問合せ、ご相談は下記よりお願いします。
https://www.ncn-se.co.jp/large/contact/
まとめ
非住宅木造においては、SE構法の構造躯体の強みを活かした構造設計により、コスト減、施工性向上を実現することができます。
SE構法は構造用集成材の中断面部材(柱は120mm角、梁は120mm幅)が標準なため、住宅と同等の部材寸法でスパン8m程度までの空間を構成できるコストパフォーマンスをうまく活用していただければと考えております。
スパンが10mを超える空間は、特注材やトラス、張弦梁などを活用することも可能です。
計画段階からNCNの特建事業部に相談することで、木造建築に関する知見をうまく利用していただき、ファーストプランの段階から構造計画を相談することで、合理的に設計実務を進めることが可能です。
集成材構法として実力・実績のある工法の一つが「耐震構法SE構法」です。SE構法は「木造の構造設計」から「構造躯体材料のプレカット」に至るプロセスを合理化することでワンストップサービスとして実現した木造の工法です。
また構法を問わず、木造の構造設計から構造躯体材料のプレカットに至るスキームづくりに取り組む目的で「株式会社木構造デザイン」が設立されました。構造設計事務所として、「⾮住宅⽊造専⾨の構造設計」、「構造設計と連動したプレカットCADデータの提供」をメイン事業とし、構造設計と⽣産設計を同時に提供することで、設計から加工までのワンストップサービスで木造建築物の普及に貢献する会社です。
株式会社エヌ・シー・エヌ、株式会社木構造デザインへのご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。