当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。
Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。
閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。
家、三匹の子ぶたが間違っていたこと
「構造計算」とは何か?【三匹の子ぶた vol.15】のインデックス
■構造計算を使った家づくりをご検討の方はこちら
「家づくり構造計算ナビ」
ここで、構造計算について図を入れてやさしく解説してみたい。難しいと思われるかもしれないが、その考え方は決して難しくはないし、理解することで、構造計算している建物としていない建物の強度が、いかに違うかがわかってもらえると思う。
法律で定められている構造計算は、大きくは以下の4つである。 許容応力度計算(ルート1) 2、許容応力度等計算(ルート2) 3、保有水平耐力計算(ルート3) 4、その他(限界耐力計算・時刻暦応答解析) 。このうち、4は特殊な建築物に利用されるケースが多いので、ここでは省くことにする。構造計算は、ルート1からルート2、ルート3とより精密に建物の強さを計算していく。 まず最初に、構造計算は以下のように「建物のすべての重さ」を想定し、調べることから始める(図表1)。
【図表1 家の重さとは?】
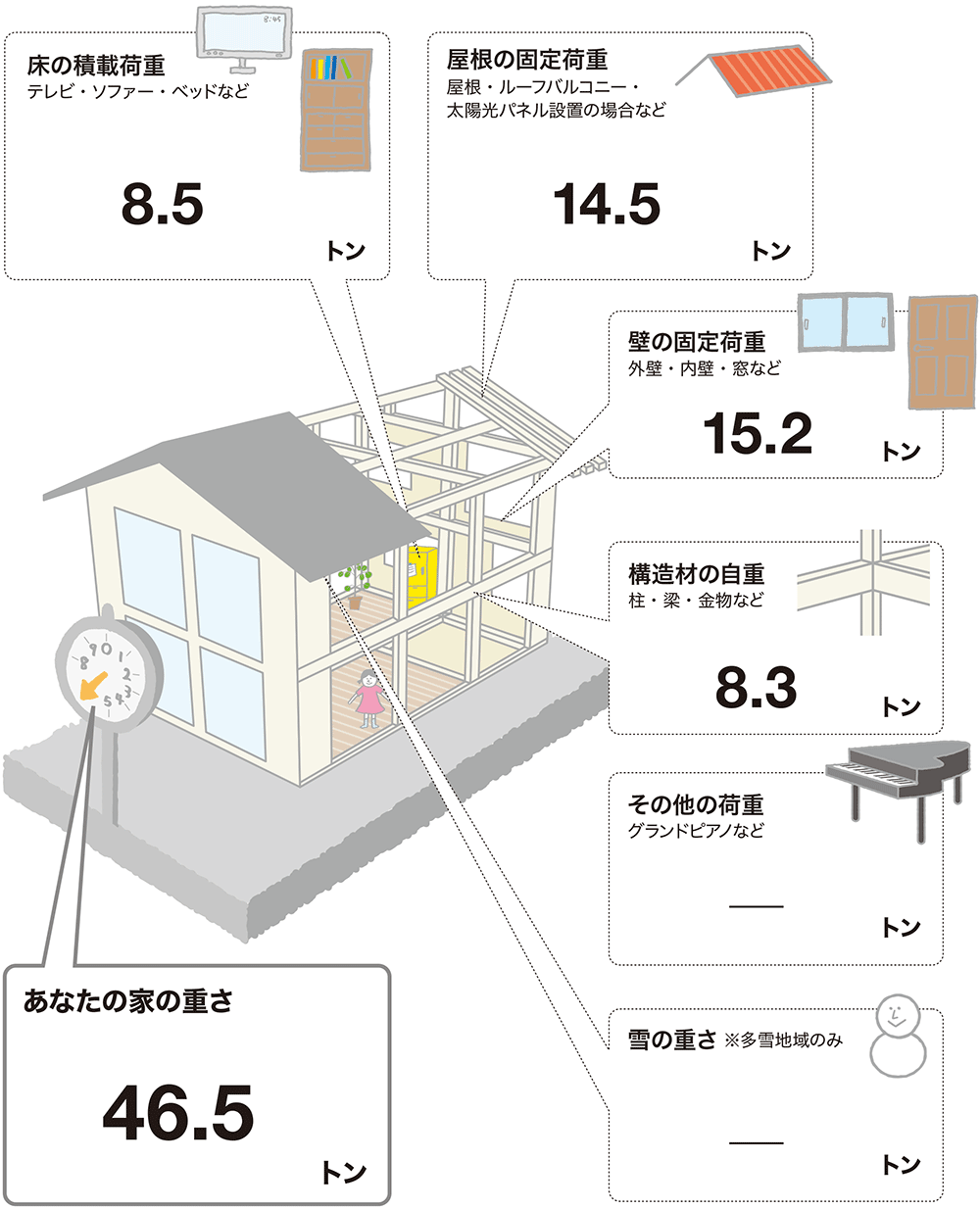
①建物の重さを調べる(建物自体の重量)。 ②建物の床に乗せる、物(人の重さや家財道具)の重さを想定する(積載荷重)。 ③雪が積もったときに屋根にかかる重さ(積雪荷重)や、グランドピアノやウォーターベッドなどのように、特に重いものの重さ(特殊荷重)を考慮する。 ④全部(建物+積載物+特殊荷重)の重さを合計する。
重さが基本になるのは、まず地球の重力に対して耐えられるか? ということ。そして、地震のときに建物に襲いかかる力は重いものほど大きくなるので、まず、建物の重さを調べないと何もわからないからだ。 1995年6月29日、韓国ソウルで5階建てデパートが突然崩壊し、死者502人を出すという大惨事があったことを覚えているだろうか。もともとこの建物は地上4階のオフィスビルにする予定だったが、建設途中でデパートに変更したため、ビル中央部の売り場の柱を大幅に取り除いてしまった。そのため、ビルの自重に耐えきれず倒壊してしまったのだ。あまりに稚拙な事件だが、地震の影響以前に、建物自体の重量を考慮しなければ十分に起こりうることなのである。
次に、「建物にかかる重さが力としてどのように伝わり、その力に耐えられるか」を調べる。 ⑤建物にどのように重さ(下向きの力)が伝わるかを調べる。 ⑥伝わった重さに、材料が耐えられるかを調べる。 そして、地震や台風が来た場合を想定して検証する。 ⑦地震が来たときにかかる力を、建物の重さから換算する。 ⑧台風が来たときに、建物にかかる力を調べる。 ⑨地震や台風のときに建物にかかる力(横向きの力)に、材料が耐えられるかを調べる。 ここまでが、ルート1の許容応力度計算である。
ここまでで、地震や台風に対して、持ちこたえる建物かどうかをまず検証する。 このうえに、次の計算が行なわれる。 ⑩地震・台風それぞれの場合に、建物がどのくらい傾くのかを計算する(層間変形)。 ⑪建物の上下階の硬さのバランスを調べる(剛性率)。 ⑫建物の重さと硬さが偏っていないかを確認する。バランスよく重さを支えられるかを調べる(偏心率)。 具体的には、通常20分の1〜200分の1以上の傾きを損壊とみなして、それ以上は傾かないように設計するわけだ。角度でいうと、0.3度程度である(図表2)。
【図表2 各階の変形の程度は、各階の数値が基準値以内であることを確認】
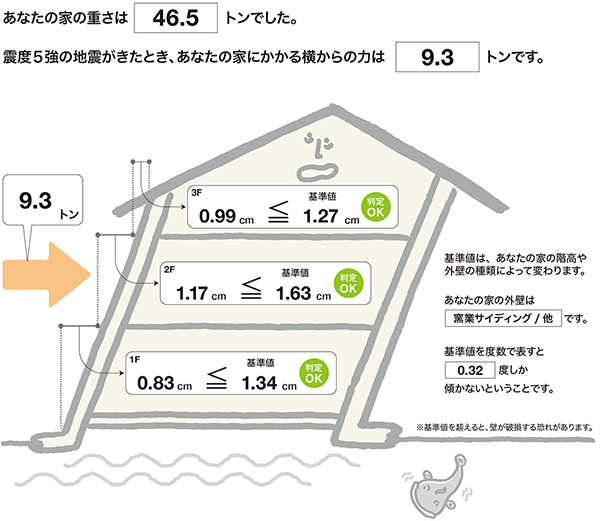
0.3度というのは3メートルの高さで0.5センチ程度しか傾かないということ。この程度の傾きであれば、揺れが収まると、また元に戻る範囲内であるということで設定されている。ボールペンでもゴルフのクラブでも、力を入れればしなるが、ある程度までなら、すぐに元に戻るのと同じ理屈だ。 また、震度5強の地震でも、地震で建具やサッシが開かなくなることがないという、安全性の検証も正確に行なう。 ここまで検証してあれば、たいていの建物は地震で倒壊することはない。ここまでがルート2の許容応力度等計算にあたる。
一般にルート2まで計算したものが、構造計算された建物と評価され、前述の能登半島地震(震度5強)でも、最大0.3度程度の変形でとどまり、半壊は免れることができる。もちろん倒壊もしない。さらに、大地震のときに多少傾いて内装が壊れても、ぺしゃんこに潰れない(全壊)かどうかを調べる方法が、保有水平耐力計算(ルート3)と呼ばれる計算方法である。 ⑬大地震が来たときの力を建物の重さから、破壊する力を換算する。 ⑭建物が地震によって瞬間的に大きく傾いたときに、どこまで粘り強く耐えられるかを調べる。 これが、ルート3の保有水平耐力計算である。
万が一、一瞬の強い揺れが来て建物が壊れるようなことがあったとしても、なかにいる人は助かるようにということだから、このルート3まで確かめた建物は、大地震でも理論上安全であるといえる。 これらの計算は、実際には一定の計算式を使うのだが、その数字(係数等)は建築基準法で「最低基準」が定められている。構造を設計する建築士や会社によっては、基準以上の係数を用いることもある。その基準づくりが企業の方針になるというわけだ。
ここまで読んで、難しくてわからないと思う方は、次に具体的な住宅で検証してみたので、我慢強く読み進んでいただきたい。
SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。
株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、
を同時に実現できる構法です。
(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)

