当ウェブサイトは、サービス向上の目的のためCookieを利用しています。
Cookieの利用に同意していただける場合は、同意ボタンをクリックしてください。
閲覧を続ける場合には、同意していただいたものといたします。
地震と住宅の新常識

耐力壁とは?木造住宅の耐震性を高める種類と配置方法をわかりやすく解説のインデックス
地震に強い家づくりに欠かせないのが「耐力壁」です。建物を横から支え、揺れによる変形や倒壊を防ぐ役割を担いますが、種類や性能、配置の仕方によって耐震性の効果は大きく変わります。
この記事では、木造住宅の耐震性を高める耐力壁の種類や配置のポイントをわかりやすく解説します。地震に備えて安全で安心できる住まいを建てたい方は、ぜひ参考にしてください。
地震や台風などで横から加わる力に耐えて、建物を守るのが「耐力壁」です。柱や梁だけでは揺れに弱く、変形や倒壊につながりかねません。そのため、耐力壁は枠の中に斜め材や板材を組み込み、壁全体で力を受け止めて分散させます。
耐力壁は外壁だけでなく、リビングや廊下など建物内部の壁にも配置され、家全体でバランスよく構造を支えます。必要な数が不足すれば耐震性が低下し、地震の際に損傷や倒壊のリスクが高まるでしょう。
安全な住まいには、十分な量の耐力壁を適切に配置することが欠かせません。

耐力壁は大きく分けて「筋交いを入れるもの」と「耐力面材を張るもの」の2種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
木造軸組工法(在来工法)で広く採用されているのが、筋交いによる耐力壁です。筋交いとは、柱や梁でつくられた四角い枠に斜め材を入れ、横からの力で枠が平行四辺形のように歪むのを防ぐ部材のことです。
取り付け方には、1本だけ入れる「片筋交い」や、X字に2本入れる「たすき掛け」があり、強さや施工性も異なります。材料費が安く施工もしやすいのがメリットですが、部材の両端に力が集中しやすく、大きな地震では折れたり外れたりする可能性があります。
筋交いが使われている壁の見分け方は「壁を叩くと空洞音がする」「細長い壁に多い」という点が一般的な目安です。
もう一つは、柱や梁で作られた四角い枠に構造用合板を釘で張り付ける方法です。壁面全体で力を受け止めるため、局所的な負荷がかかりにくく、構造体を保護しやすいのが特長です。さらに壁全体に断熱材を入れられるため、断熱性能の向上にもつながります。
デメリットは、材料費が高いこと。また通気性が低く内部結露を起こしやすいと言われますが、近年は通気性のある素材も使われるようになっています。
主に外壁部分に採用されます。
「壁倍率」とは、建築基準法で定められている耐力壁の強さのことです。数値が大きいほど耐力が高く、耐震性の高い壁であることを示します。
壁倍率は、筋交いの太さや本数、使われる耐力面材の種類などによって決まり、0.5〜5.0の範囲で設定されます。
木造における代表的な耐力壁と壁倍率
| 種類 | 壁倍率 | ||
| 筋交い | 厚さ1.5cm以上・幅9cm以上 | 1.0 (たすき掛け2.0) |
|
| 厚さ3.0cm以上・幅9cm以上 | 1.5 (たすき掛け3.0) |
||
| 厚さ4.5cm以上・幅9cm以上 | 2.0 (たすき掛け4.0) |
||
| 9cm角以上 | 3.0 (たすき掛け5.0) |
||
| 耐力面材 | 0.5〜5.0 | ||
構造用合板の場合は国土交通大臣の認定が必要で、壁倍率は0.5〜5.0の範囲内で定められます。筋交いと耐力面材を併用した場合は壁倍率を合計でき、上限は7.0です。筋交いと耐力面材を併用すると壁倍率は高くなりますが、壁が分厚くなり居住スペースを圧迫するというデメリットもあります。
設計の際には「耐力壁の長さ × 壁倍率」で耐震性を数値化して確認します。つまり、どんな耐力壁をどこに、どのくらい配置するかを判断する重要な基準が壁倍率なのです。
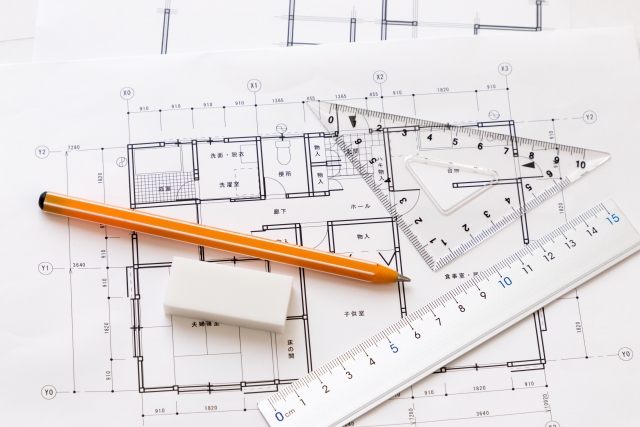
地震に強い木造住宅を実現するには、耐力壁をどのように配置するかが重要です。ここでは、設計時に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
耐力壁は、量が不足すると建物全体の強度が足りなくなります。そのため、まずは建築基準法に基づく「壁量計算」によって必要な量を確認し、X方向・Y方向の両方にバランスよく確保することが大切です。
耐力壁は数を増やすだけでなく、建物の平面バランスを整えることが重要です。特定の一箇所に集中すると、地震時に建物全体がねじれるように変形し、倒壊の原因となる可能性があります。
基本は、建物の四隅を耐力壁で固めること。そのうえで全体のバランスや間取りの使いやすさを考慮しながら配置を調整します。
耐力壁の配置は、平面だけでなく立面のバランスも重要です。上下階で耐力壁の位置が揃っていないと、力がスムーズに伝わらず、一部に大きな負担が集中します。その結果、地震の際に1階部分が潰れるなどの重大な被害につながることもあります。
間取りを計画するときには、平面図だけでなく上下階の対応関係を確認し、耐力壁の位置を揃えるようにしましょう。

耐力壁を計画する際、建物の高さや階数、延床面積が一定以上の場合、専門的な知識を用いた構造計算によって安全性を確認する必要があります。一方で、木造・階数2以下・延床面積300㎡以下等の建物では、構造計算は必須ではありません。この場合は、建築基準法施行令に定められた「仕様規定」で構造の安全性をチェックします。仕様規定では耐力壁の量を確認する「壁量計算」などの方法が示されています。2000年以降は、平面上での耐力壁のバランスを確認する「四分割法」または「偏心率」でのバランス計算も必須となりました。上下階のバランスは「直下率」で確認できますが、建築基準法上の規定は設けられていません。
建物に必要な耐力壁の量を確認するのが「壁量計算」です。地震や風に抵抗するために必要な壁量を算出し、設計上の耐力壁がその量を満たしているかどうかをチェックします。
壁量計算では耐力壁の強さを表す「壁倍率」を使い「耐力壁の長さ × 壁倍率」で実際の壁量を求めます。
平面上の耐力壁の配置バランスを確認する方法が「四分割法」です。建物のX方向・Y方向をそれぞれ4つに分け、外周から1/4の範囲に配置された耐力壁の長さが十分かどうかをチェックします。
耐力壁は建物の中央よりも外周に配置した方が水平力に有効に抵抗できるため、四分割法では外周部に着目します。
偏心率は、建物の重心(重さの中心)と剛心(強さの中心)のズレを数値化して確認する方法です。偏心率が大きいと、地震の際に建物がねじれてしまうリスクが高まるため、0に近くなるように設計します。
建物が複雑な形をしている場合は、四分割法だけでは確認が難しいため「偏心率」を用いて安全性を検証します。
上下階の柱や耐震壁の位置が揃っているかどうか確認するのが「直下率」です。
直下率が高ければ力がスムーズに伝わり、直下率が低いと1階部分に負担が集中して倒壊リスクが高まります。
直下率に関する法的規定はありませんが、安全な設計のためには上下階の柱や耐力壁をなるべく揃えることが推奨されます。
地震に強い木造住宅の工法として注目されているのが「SE構法」です。SE構法で採用されている耐力壁の4つの特徴をお伝えします。
| SE構法とは?
従来はRC造などでよく使われてきた「ラーメン構造」を木造に応用した工法で、柱と梁などの接合部を「剛接合」にすることで強度を高めています。 SE構法では構造計算が必須とされていない規模も含めて、全棟で構造計算をするのも特徴。すべての部材の強度がわかった状態で、立体解析構造計算プログラムを用いて建物の変形やねじれ、バランスなどを検証します。 |
SE構法では、一般的な在来工法の耐力壁の約3.5倍の強度をもつ独自の耐力壁を採用しています。少ない枚数でも十分な耐震性を確保できるため、開放的な間取りや大空間の設計にも対応可能です。
柱と梁の接合部を剛接合にすることで、建物全体の強度を高めています。さらにSE構法では、すべての建物で構造計算を実施。変形やねじれ、力の流れを立体的に検証した上で設計されるため安全性がより確実になります。
耐力壁には強度の高い1級構造用合板を使用し、せん弾力に優れるCN釘でしっかり固定。繰り返す地震の揺れにも釘穴が広がりにくく、長期間にわたり耐力を維持できます。
強度の高い耐力壁を用いることで、壁の量を減らしても十分な耐震性を確保できます。吹き抜けやスキップフロアなど、開放的で居心地の良い空間づくりが可能です。

地震に強い家を建てるためには、耐力壁の量や配置バランスがとても大切です。
SE構法で採用しているのは、筋交いを使わない独自の耐力壁。一般的な筋交いによる耐力壁の3.5枚分の強度をもち、耐震性の向上に大きく貢献します。
少ない耐力壁でも耐震性が担保されるので、開放的な間取りにしたい方、構造的な制約が少ないなかで自由な家づくりをしたい方はぜひ検討してみてください。
SE構法は、木造住宅の構造技術です。丈夫な材料とラーメン構法による強い構造躯体と、一棟一棟に対する基礎から上部までの厳密な構造計算を行う点が最大の特長です。私たちの特長を是非ご覧ください。
株式会社エヌ・シー・エヌが開発した構法で、集成材とSE金物による堅牢な構造媒体を持ちすべての建造物に対してひとつひとつ構造計算(許容応力度等計算)を行うことで、
を同時に実現できる構法です。
(施工は全国の登録工務店でしか行うことができません。)

