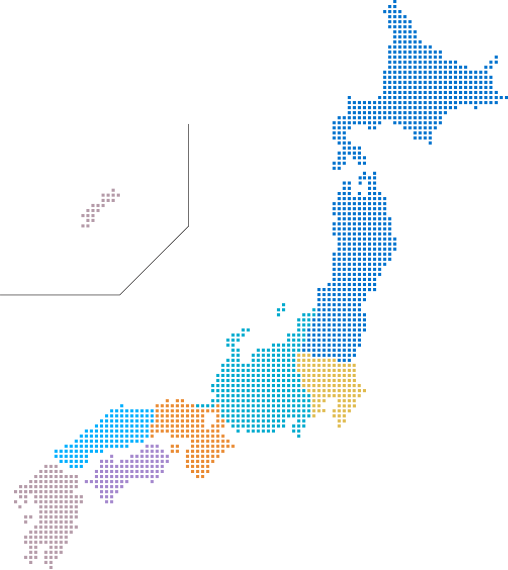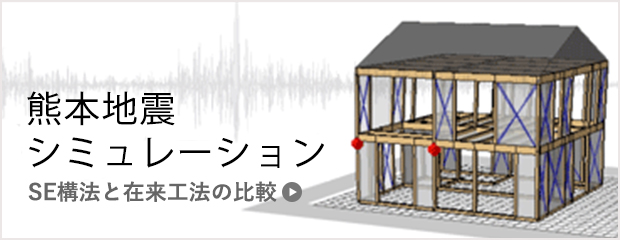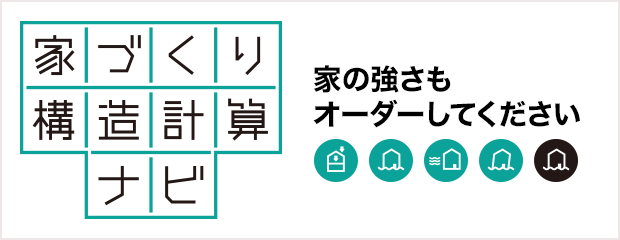2020/03/03インフォメーション
【セミナーレポート】 『木造の設計プロセス』実務から考える中大規模木造セミナー
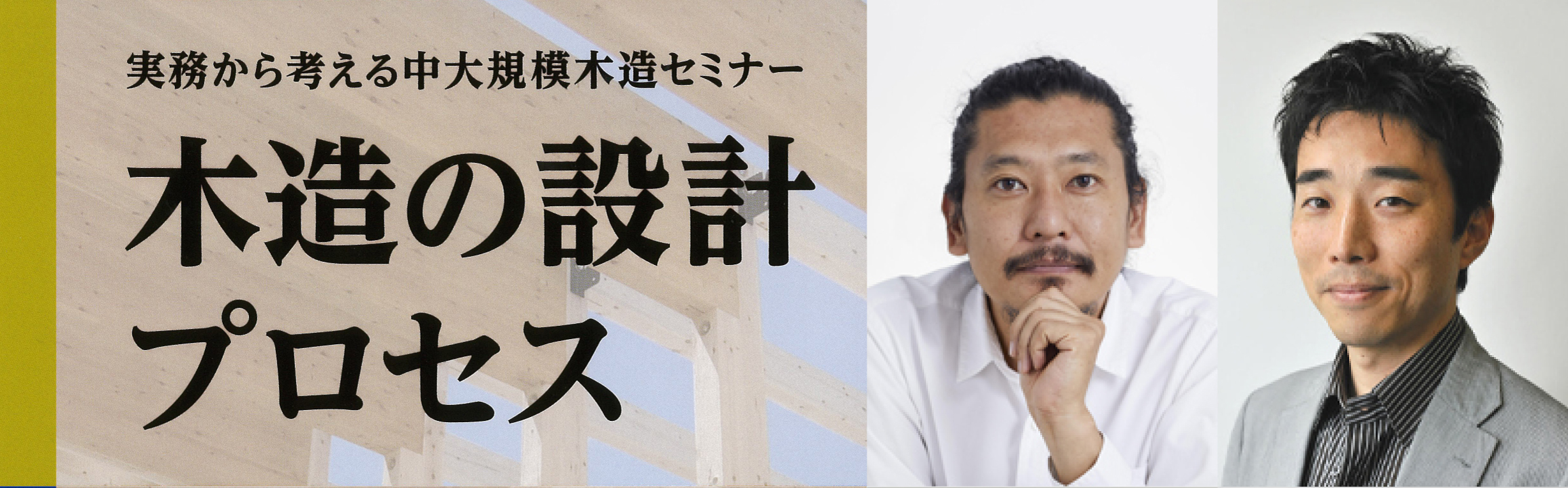
本セミナーは、循環型社会で建築に木を使う重要性が見直され、さまざまな用途で急激に増えつつある中・大規模木造建築において、実務の視点から今後の建設の在り方を考えるべく、日経BP総合研究所主催にて2020年2月25日にAP新橋(東京都港区)で開催されました。
エヌ・シー・エヌは、木造耐震設計事業において高度な構造計算と、独自の建築システム「SE構法」により全国の工務店を通じて住宅から中大規模木造建築物を提供する企業として本セミナーに協賛いたしました。
◆「風景でつくり、風景をつくる。」 新しい木がつくる新しい空間とは?

カリキュラムの第一部、マウントフジアーキテクツスタジオ 原田 真宏氏による基調講演「新しい木がつくる 新しい空間」では、原田氏が手掛けた豊富な実例を元に、造作家具や大きな梁せいを構造体の一部としたり、CLTを立方体に組んだフレームをずらしながら積み重ねて立体的で複雑な空間を作るなど、様々な木の使い方が紹介されました。
実例紹介の一つ『Chiryu After school』は東海道五十三次の39番目の宿場町であった知立市のまちづくりの一環として建築された学童保育施設(=寺子屋)です。地域の持つ歴史性から「歴史的文脈を継承すること」「自然科学の原理に即すること」を示すべく設計された2本の柱を軸とする懸垂曲線の屋根架構は、木の持つ優しくやわらかい風合いが近隣の社寺に調和しつつも自然科学の幾何学的な姿を見せています。
原田氏は山や自然現象などからインスピレーションを得て設計することが多いとのこと。『道の駅ましこ』は陶芸に代表される民芸運動で知られている栃木県益子町に建てられた建築物で、屋根を周囲の山並みの稜線と合わせた形状とし、最大スパン32mの屋根架構は地元の八溝杉を使った集成材を採用しました。街側から見て駐車場が見えないように配慮するなど、景観を壊すことなく土地の風景と調和するよう細部にわたり設計しました。
「ここから山を眺めた地元の人から、『自分の住んでいるところはこんな素晴らしい場所だったんだ。』と言われたことが本当に嬉しかったですね。建物を介して地元で作ったものや人々がつながる、建築にはそんな力があると思います。建築は『大きい民芸品』。景観を純化し街の価値を上げるもので在りたいと思っています。」
ニーズに合わせて多様に素材を選択できること、プレカット等の発達により施工者が少ない地域でも建築が可能なこと、相手部材に合わせて組むことができるフレキシブル性など、中大規模木造建築には様々なメリットがあるという原田氏。現在着手中の建築でもさらにまた新しい木の可能性を拡げている最中です。
—————————————————————————————–
<紹介作品>
・焼津の陶芸小屋(2003年)
・おおきな家(2006年)
・海辺の家(2013年)
・Shore house(2012年)
・near house(2010年)
・立山の家(2016年)
・LIAM FUJI(2019年)
・傘の家(2016年)
・母の家(2013年)
・Chiryu Afterschool(2016年)
・道の駅ましこ(2016年) ほか
—————————————————————————————–
◆「中大規模木造=難しい」を解決する、中大規模木造の設計プロセス
次にエヌ・シー・エヌ 特建事業部 部長 福田 浩史より、「中大規模木造の設計プロセス」と題して、実際の設計プロセスに応じた問題点と押さえるべきポイントについて実務講演を行いました。

「中規模木造を建築する際の設計・生産の課題として、構造設計者の不足、接合部の未規格化、材料の調達難、見積もり精度不足、プレカット工場での加工図作成不可、受注後の加工手戻り、製造工場の能力や品質レベルの不明確さ、施工の不得手などが挙げられます。これらを解決すべく、エヌ・シー・エヌのSE構法では木構造におけるシステム化を実現しました。構造設計、積算、調達、加工、施工の一気通貫のワンストップサービスで、『正しく構造設計し、正しく生産、提供し、正しく施工を行う』という仕組みを構築しています。」
数多くの中大規模木造を手掛けた経験・実績から、中大規模木造は決して難しいものではありません。難しいと感じてしまう要因を解決するために、建築物の規模や用途、基準に適した材料・構造形式の選定方法、構造計画・材料計画での注意点やコストダウン成功例、適切な加工工場・施工業者の選定方法など、具体的なポイントについて説明しました。
「2020年2月に設立した株式会社木構造デザインでは、SE構法だけでなく構法を問わずすべての中大規模木造建築物についてワンストップで支援可能です。日本に美しくて強く、端正な木造建築を普及させるために少しでも力になれればと考えております。出来る出来ないなどのお問合せレベルでも結構ですのでぜひお気軽にお声がけください。」
◆木造建築が当たり前になると何が変わる?それぞれの視点からの木の建築
パネルディスカッションでは、日経BP総合研究所 小原 隆氏の進行のもと、マウントフジアーキテクツスタジオ 原田 真宏氏、Arup 金田 充弘氏、株式会社三橋設計 天木 順彦氏、エヌ・シー・エヌ 福田 浩史による、建築家、構造家、メーカーそれぞれの視点から「木造建築を当たり前にするには」何が必要かをテーマにトークセッションが行われました。

「公共建築物木材利用促進法の施工やコスト面への影響、また企画のイメージアップとして建築物を木で作ってほしい、という依頼が近年増えています。木造の中大規模建築はまだまだ知見不足のため建築過程ではいろいろな問題が起こりますが、できた後は皆が木の建築を喜びます。木造建築が当たり前になるには、『木造で建築するのが良いこと』であることを施主にデータとして説明できるような知見の共有が必要です。」(原田氏)
「地元の木を使う建築は地元の人に愛されますが、適材適所で正しい値段で建築することも大切です。そういった意味では都市部の方が、材料も入手しやすく木造+RC造などの組み合わせによる木造建築物が建てやすい傾向にあります。木造を長く持たせるには手間ひまをかけることが必要。『メンテナンスフリー』ではなく『スーパーハイメンテナンス』な地域密着型の木造建築物を通じて寛容な世の中になってほしい。」(金田氏)
「名古屋では木材利用促進法施工後も木造の中大規模建築物がそれほど増えていないのが実情。前例が無いことで、特に1000m2を超える建築物は嫌がられる傾向にあります。三橋設計ではSE構法で『こども園あるこ』や『きたなかねこども園』を設計しました。BIMの活用により意匠設計や構造・意匠間の連携がスムーズでした。」(天木氏)
「構造設計者が中大規模木造建築に移行しづらい理由を無くしていき、こうした市場に地場の工務店が参入し、多くの方が建てられるようになってほしい。」(福田)
木造建築は持続可能な社会を作るだけではなく、木造建築が当たり前になり、地場産の木材を使って地元の工務店・大工が建てること、それをメンテナンスして大切に使っていくことで、建築業界に現象として新たな「豊かさ」を生み出すことができるかもしれません。
※本セミナーは3月16日に同内容にて大阪で開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を鑑みて中止といたしました。
■実務から考える中大規模木造セミナー『木造の設計プロセス』
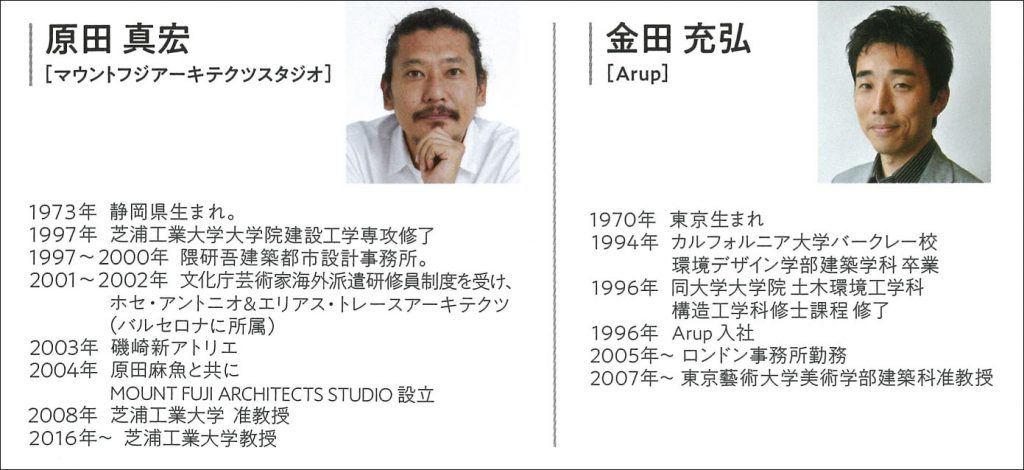
【登壇者】
【カリキュラム】
■開催概要
【開催日時】 2020年2月25日(火)13:30ー17:00
【会 場】 AP新橋(東京都港区新橋1‐12ー9 A-PLACE新橋駅前)
【主 催】 日経BP総合研究所
【協 賛】 株式会社エヌ・シー・エヌ
【協 力】 日経アーキテクチュア
【定 員】 200名(東京、大阪ともに)
【参 加 費】 無料